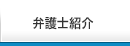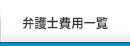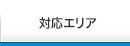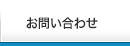特別縁故者に関する裁判例の分析②
次に,特別縁故者であることを否定した裁判例を紹介します。
東京高等裁判所平成26年1月25日判決は,被相続人の生前に一定の交流があったものの特別縁故者であるとまでは認められないと判示した事例です。
事案の概要は以下のとおりです。
① Xは被相続人の従妹の養子である(Xが本家,被相続人が分家の関係にある。)。
② Xと被相続人は継続的な親戚付き合いがあった。
③ Xは,被相続人の死後,被相続人の葬祭や被相続人等の維持管理をした。
このような事案で,裁判所は,Xと被相続人の交流の程度からすると,Xが被相続人の死後,被相続人の法要や被相続人宅の庭木等の維持管理のため一定の労力と費用をかけ,今後も継続する意思を有していることなど被相続人の死後のXの貢献を加えて検討しても,Xを特別縁故者と認められないと判示しています。
前のコラムでも説明したとおり,特別縁故者に該当するというためには,「被相続人と具体的かつ現実的な交渉があり,その者に相続財産の全部又は一部を分与することが被相続人の意思に合致するとみられる程度に被相続人と密接な関係にあった」ことが要件となります。上記の裁判所の判断の前提には,Xが主張した「継続的な親戚付き合い」程度では,具体的かつ現実的な交渉とまではいえないという理解があるものと考えられます。特別縁故者に該当するためには,通常の親戚付き合いを超えた交流が必要になるのです。
では,通常の親戚付き合いを超えた交流とは,どのようなものでしょうか。この点は他の裁判例等を見ても必ずしも明確にはなりません。ただ,一般論として,今日,親戚関係自体が希薄となっていて,通常の親戚付き合い自体,交流の程度が薄くなる傾向は否めないと思います。特別縁故者の認定においてもこのような時代の趨勢等も考慮して判断されるものと思われ,「通常の親戚付き合いを超えた交流」のハードルも昔よりは低くなっているのではないでしょうか。過去に通常の親戚関係に過ぎないと判断された事案についても,今日の視点でみれば,通常の親戚関係を超えた付き合いと判断されるような事案も出てくるかもしれません。
いずれにせよ,特別縁故は,被相続人とどれだけの交流があったかどうかという点が極めて重要になってきます(続く)