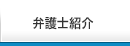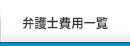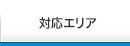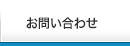Archive for the ‘未分類’ Category
死亡危急時遺言について
1 死亡危急時遺言とは,死期が迫り署名押印ができない遺言者が口頭で遺言の内容を証人に伝え,証人がそれを書面化する方式により作成する遺言のことをいいます(民法976条)。
自筆証書遺言は,遺言者が全文,日付及び氏名を自書して,押印する必要があります。そこで,遺言者の死期が迫って,署名押印することができない場合には,自筆証書遺言を作成することができません。死亡危急時遺言は,遺言者が,死期が迫って,署名押印をすることができない場合であっても,一定の要件を満たせば作成することができる遺言です。
このような遺言を作成する機会は多くはありませんが,私は,この方式による遺言を作成し,遺言者の意思に沿った財産の承継を行うことができた事例を扱ったことがあります。以下では,死亡危急時遺言の概要や私らが取り扱った事例について解説します。
2 死亡危急時遺言の要件は,①証人3人以上の立会いをもって,その一人に遺言の趣旨を口授すること,②口授を受けた証人がその内容を筆記すること,③遺言者及び他の証人に読み聞かせまたは閲覧させること,④各証人がその筆記の正確なことを承認したのち,これに署名押印することです。
そして,以上の方式でなされた遺言は,遺言の日から20日以内に証人の一人または利害関係人から請求をして家庭裁判所の確認を得るという手続を行う必要があり,これをしなければ遺言の効力が失われます。この手続きは,遺言が遺言者の真意に出たものかを判断する手続になります。死亡危急時遺言は,簡易な方式で作成される遺言ですので,遺言者の真意に合致するか判断する手続が必要となるのです。そこで,遺言者の真意に反することが明らかな遺言を排除する趣旨で,裁判所の確認の審判を得るという手続が必要になっています。
なお,裁判所の確認の審判を経ても,上記①ないし④の方式に違反する遺言であることが確定するわけではありませんので,方式に違反することを理由として,遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起して争うことは可能です。
医師の立会いは要件とされておらず,医師の立会いがなくても,直ちに遺言が無効となるものではありませんが,遺言者の死期が迫っており,意思確認が困難なときに作成する遺言書になりますので,できる限り,医師が立ち会うよう配慮した方がよいと思われます。
3 私が取り扱った事例では,遺言者(Aさん)は,配偶者や子がおらず,それまでAさんの面倒を見ていた甥(Bさん)に対し,全財産を譲渡したいとの希望を持っておりました。Aさんは,体調を崩して入院することになったため,Bさんに対し,全財産の管理を依頼するとともに,自分が死亡した場合には,全財産を譲渡することを伝えました。
AさんとBさんは,このような財産管理や財産の譲渡について明確にするために,財産管理契約書,任意後見契約書,公正証書遺言を作成すべきであると考え,私らに,これらの書面の作成を依頼しました。
その後,私らは,Aさんに会って打合せをするために,Aさんの入院している病院を訪問しましたが,病院関係者から,Aさんの容体が急激に悪化し,今日あるいは明日が山であるという説明を受けました。前日,Aさんは,見舞いに来た同級生二名との歓談を楽しんでおり,Aさんの体調が順調に回復していると聞いていましたので,Aさんの容体が急変したことは,私らにとっても,Bさんにとっても,まさに青天の霹靂でした。
病院関係者から事情を聴取したところ,私らは,Aさんの意識ははっきりしているものの,とても署名や押印をすることができる状態ではないことが分かりました。また,私らとしては,公正証書遺言を作成するような時間的な余裕がないと考えました。一方,BさんはAさんの甥であり,相続権がないため,このままだとAさんが望むBさんへの財産の承継が実現しないことになります。
そこで,私らは,死亡危急時遺言の制度を利用することにして,一度事務所に帰って,必要書類の作成,証人,立会人の手配等の準備をしたうえで,再度,病院を訪問し,危急時遺言の作成にとりかかりました。
Aさんは,意識こそはっきりしていたものの,筆記,押印は不可能でした。私らが,Aさんに話かけたところ,ゆっくり時間をかけて話をすれば,Aさんとの意思疎通が可能な状態でしたので,何とか,死亡危急時遺言を作成することができました。
Aさんは,1日後に亡くなりました。その後,私らは,作成した死亡危急時遺言についての確認の審判の申し立てをおこない,確認の審判を得ることができました。その後,遺言の内容にしたがい,また,Aさんの意向どおり,BさんがAさんの財産の全部を取得することができました。
大沢樹生さんと喜多嶋舞さんの争いが訴訟になった場合の勝負の行方
父子関係についてのコラムが続いておりますので,巷間を賑わせている大沢樹さんと喜多嶋舞さんの事件の今後の見通しについて少し説明したいと思います(大沢さんとの父子関係が争われている子をA君とします。)。
現在,大沢さんが,親子関係がないことの確認を求める調停を申し立てているようです。調停は話合いですが,これまでの経緯からすると,話合いがまとまらない可能性が高いと思います。その場合,大沢さんは,訴訟を提起するものと考えられます。
それでは,訴訟になった場合,どちらが勝つのでしょうか。
まず,大沢さんとA君の間に生物学的な親子関係があって,大沢さんが証拠として提出するであろうDNA鑑定結果が誤りであるということであれば,当然,大沢さんは敗訴になります。
逆はどうでしょうか。つまり,大沢さんとA君の間に生物学的な親子関係がなくて,大沢さんが提出した証拠でそれが証明できる場合です。実は,この場合であっても,大沢さんが敗訴する,というのが法律家の一般的な見方だと思います。それはなぜでしょうか。
実は,父子関係を否定するために争う訴訟形態としては,親子関係不存在確認の訴えのほか,嫡出否認の訴えというものがあります。嫡出否認の訴えは,いわゆる「推定される嫡出子」との間の法律上の父子関係を否定する唯一の方法とされています。
逆にいえば,「推定される嫡出子」の場合には,父子関係不存在の訴えを提起して父子関係を否定することはできないとされているのです。そして,「推定される嫡出子」とは,婚姻成立後200日以内,婚姻解消後300日以内に妊娠した子どものことを言います。そして,A君は,大沢さんと喜多嶋さんお二人の婚姻から7か月後に出生したとのことですので,「推定される嫡出子」に該当します。そこで,大沢さんとしては,「嫡出否認の訴え」を提起しなければ,父子関係を否定することはできません。
ところが,「嫡出否認の訴え」を提起することができるのは,子の出生を知った時から1年以内とされています。そうすると,大沢さんは,嫡出否認の訴えを提起することはできません。
一方,A君は「推定される嫡出子」なので,大沢さんとしては,親子関係不存在確認の訴えを提起することもできません。結局,大沢さんとしては,親子関係を否定する手段がないということになります。
以上は,法律家の間で一般的に認知されている考え方です。この考え方によれば,仮に,大沢さんとA君の間に生物学的な父子関係がなかったとしても,手続論の観点から,来るべき訴訟において大沢さんは決定的に不利益な立場になります。
私自身,当初はそのように思っていたのですが,最近は訴訟の行方が分からなくなってきました。それは,朝日新聞の1月19日付の以下の記事を見たからです。記事の内容は以下のものです。
「DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば、父子関係を取り消せるかが争われた訴訟の判決で、大阪家裁と大阪高裁が、鑑定結果を根拠に父子関係を取り消していたことがわかった。いったん成立した親子関係を、科学鑑定をもとに否定する司法判断は、極めて異例だ。
訴訟は最高裁で審理中。鑑定の精度が急速に向上し、民間機関での鑑定も容易になるなか、高裁判断が維持されれば、父子関係が覆されるケースが相次ぐ可能性がある。
最高裁は近く判断を示すとみられ、結果次第では、社会に大きな影響を及ぼしそうだ。」
現行法上,いかなる意味においても,父子関係を「取り消す」ことはできません。その意味で,この記事の内容には明確な誤りがあります。そのこともあり,記事の意味するところは,必ずしも明確ではありません。
ただ推察するに,大阪家庭裁判所,大阪高等裁判所において, DNA鑑定で血縁関係がないことが証明されていれば,親子関係不存在確認の訴えを提起して,法律的な父子関係を否定することができるという判断がされたということなのだろうと思います。
親子関係不存在確認の訴えは,嫡出否認の訴えのように提訴期間の制限等の特別な要件が課せられていません。朝日新聞の記事を見る限り,推定される嫡出子であったとしても,DNA型鑑定で血縁鑑定がないと証明されれば,嫡出否認の訴えをすることなく,親子関係不存在確認の訴えを提起して,親子関係を否定することができると読めるのです。
記事の中で,高裁の判断が維持されれば,「父子関係が覆されるケースが相次ぐ可能性がある。」と記載されていますが,大沢さんの件でDNA型鑑定により血縁鑑定がないと判断された場合には,まさにこのケースに該当します。すなわち,大沢さんの勝ちです。
以上のような高裁判断は,嫡出否認の訴えを事実上形骸化することを目的としたもので,最高裁判所で維持されるのかどうか,確定的なことは言えません。ただし,このような高裁判断が出ていること自体,嫡出否認の訴えというものの意義が根本的に揺らいでいるように思います。
親子とは?
・生物学的親子関係と法律的親子関係
いくつか親子関係に関するコラムが続きました。
ところで,そもそも,親子とは何でしょうか。多くの人は,「血のつながりがあること」と回答すると思います。「血のつながりがあること」という意味での親子関係を,ここでは,生物学的親子関係ということにします。実は,この生物学親子関係は,法律上親子関係が認められる場合(これを法律的親子関係ということにします。)は,必ずしも,一致しません。
・生物学的親子関係はあるけれど法律的な親子関係でない場合
まずは,生物学的親子関係ではあるけれど,法律的な親子関係でない場合とはどのような場合があるでしょうか。いわゆる認知を受けていない婚外子(非嫡出子)の父子関係はこれに該当します。
例えば,未婚のAさんがBさんの子(生物学的な子)Cを出産した場合を考えてみます。この場合,AさんとCさんの母子関係は,分娩の事実により当然に発生します(Aさんが,Cさんを認知することなく,母子関係が発生します。)。一方,認知という手続がない限り,BC間に法律的な親子関係は発生しません。Aさんが,Bさんに対し,Cと生物学的親子関係が認められるというDNA鑑定結果を持っていって,親子なのだから養育費を支払えと主張しても,そのような主張は認められません。Aさんとしては,まず,Bさんに認知をしてもらうか,あるいは,強制的に認知をさせて(要は,裁判をして),法律的親子関係を発生させ,養育費を支払わせるという手続をとる必要があるのです。つまりこの場合,
生物学的親子関係+認知=法律的親子関係
という関係が成り立つのです。
・法律的な親子関係ではあるけれど生物学的には親子関係がない場合
それでは,逆に法律的な親子関係ではあるけど,生物学的親子関係はない場合とはどのような場合があるでしょうか。まず思いつくのが養子縁組をした場合で,これは分かりやすいと思います。
さらに,嫡出子の場合,父子関係が争える要件が限定されていることとの関係で,生物学的親子関係は認められないけれども,法律的な親子関係がある状態が継続するということがありえます。
例えば,以下のような設例で考えてみたいと思います(民法Ⅳ・内田貴176頁をベースにした事案です。)。
設例
春子は夏夫と結婚後,会社勤めを始めたが,職場の同僚冬彦と情交関係を持つようになった。やがて春子は冬彦の子と思われる長男太郎を出産したが,夏夫が自分の子であると信じて喜んでいたので,打ち明けられなかった。やがて,春子と夏夫は不和になり,太郎の親権者を春子と定めて協議離婚をした。離婚後,太郎の出生後10年余りたってから,夏夫は,太郎が,自分と似ていないと思うようになり,DNA鑑定を行ったところ,太郎と自分の間に生物学的親子関係は認められないという鑑定結果を得た。
問題の焦点は嫡出否認の訴えという制度です。
婚姻中に妻が妊娠した場合,その子は夫の子である蓋然性が高いため,夫の子であると推定されます(民法772条1項)。つまり,上の事例では,太郎は,冬彦の子であると推定されます。太郎のように,嫡出子であると推定される子を推定される嫡出子といいます。もちろん,上の事例のように,推定される嫡出子だからといって夫の生物学的親子であるとは限りません。
それでも,推定される嫡出子と夫の法律的な親子関係を覆すためには,嫡出否認の訴え(民法774条,775条)という特別な制度を利用する必要があります。これ以外の方法で,推定される嫡出子と夫の法律的親子関係を覆す手段はありません。
それでは嫡出否認の訴えというものは,どのような制度でしょうか。関連する条文を見ていきたいと思います。
第772条の場合において,夫は,子が嫡出であることを否認することができる。
民法775条
前条の規定による否認権は,子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。・・・
民法776条
夫は,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,その否認権を失う。
民法777条
嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
つまり,少なくとも条文上は
◇嫡出否認の訴えは,父しか提起できない。
◇父が嫡出子であることを認めてしまったら,嫡出否認の訴えを提起することができない。
◇嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から(ただし,この点については争いがあります。最近は,他人の子であると知った時から起算するという解釈をとる裁判例も少なくないようです。),1年間の間だけ提起することができる。
と読めるのです。すなわち,以上のような嫡出否認の要件に該当しないのであれば,嫡出否認の訴えを提起することができず,したがって,夫と子は生物学的親子関係がなくても,法律的親子関係があるという状態が続いていくのです。
設例の事案でいえば,少なくとも,夏夫が,太郎との間で生物学的親子関係がないと認識したときから1年以上経過すると,夏夫は,親子関係を争うことができなくなり,夏夫,太郎は法律的な親子であるという状態が継続していくことになるのです。
ここまでは,これまでの一般的な考え方でした。ただし,最近では以上のような考え方とは異なる考え方も有力になってきています。この考え方は,端的に言えば,DNA鑑定等により,生物学的親子関係が認められないのであれば,法律的親子関係を覆すことを認めるべきだというものです。今後のことは何ともいえませんが,裁判所は,このような生物学的親子関係の有無を重視した判断に傾きつつあるという気がします。
元横浜ベイスターズの駒田徳広さんが当事務所に取材に来られました。
 元横浜ベイスターズの駒田徳広さんが当事務所に取材に来られました。
元横浜ベイスターズの駒田徳広さんが当事務所に取材に来られました。
内容はカンパニータンク(2014年4月号,国際情報マネジメント)に掲載される
予定になっています。
最高裁平成26年1月14日第三小法廷判決について
先日,認知の無効に関する重要な最高裁判所の判決が出ました。
争点は,
「血縁上の親子関係がないことを知りつつ認知した父親でも,認知の無効を主張することができるか」
という点でした。
判決は,父親が血縁関係のないことを認識して認知したとしても,原則として,認知の無効を主張することができると判示しました。
これまでは,このような場合に,父親からの認知無効を認める見解と認めない見解で争いがあり,どちらの見解も有力に主張されていました。
無効の主張を否定する見解の論拠はいくつかありますが,一番重要なものは「子の地位の安定」です。
要するに,父親が,血縁関係のないことを知りつつ認知をして,一応父子関係を発生させたのに,気が変わったからといって,認知の無効を主張できるとなると,子の地位があまりに不安定になるということです。認知をして法律的な親子になると扶養義務が発生するなどの一定の効果が発生します。自分の意思で認知をした父親が勝手に認知の無効を主張して,これらの法律関係を無くしてしまうことは許されないのではないかということです。
この判決の上告人(認知された子どもです。)も,「気まぐれな認知と身勝手な無効の主張を許すこと」は相当でないと主張しています。
これに対して,最高裁は,「認知者が認知をするに至る事情は様々であり,自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。」「認知を受けた子の保護の観点からみても,あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく・・・」と判示して,原則として父親からの無効主張を認めています。
もっとも,裁判所も,「子の地位の安定」という点を配慮していないわけではありません。裁判所は,「具多的な事案に応じてその必要がある場合には,権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である」と判示しています。「気まぐれな認知と身勝手な無効主張」により子の地位の安定が害される場合には,権利濫用の法理により,無効主張を制限する可能性があることを示しました。
非常にざっくり言いますと,この判例は,法律上の親子関係を発生させるかどうかについて,生物学的親子関係(血縁上の親子関係)があるかどうかを重視したもので,近年の裁判例の傾向と一致するように思います。生物学的親子関係の重視という傾向は今後も続いていくものと考えられます。生物学的親子関係は,DNA鑑定によって明らかになるもので,結局,DNA鑑定の結果が結論に反映されるような傾向が続くものと思います。
親子関係の不存在の争い方
最近元アイドルグループのメンバーの親子関係をめぐる争いが話題となっています。親子関係をめぐる争いは,ほとんどの場合父子関係の有無についての争いです。
一般の方に知られていないのは,父子関係の争い方です。
たとえば,巷間を賑わしているアイドルグループと同じような事例で考えてみたいと思います。
・男性A Cの戸籍上の父親,Bの元夫
・女性B Cの母親,Aの元妻
・子C
とします。AとBは離婚しています。このような状況で,Aが,Cと血縁関係がないことを確信するに至った場合,どのような手段をとることができるでしょうか[1]。どういう方法で戸籍を修正することができるでしょうか。
まず,Aとして考えるのは,BやCと交渉して,AC間に親子関係がないことを認めてもらうことだと思います。
しかし,仮に,AとBやCとの間で,AC間に生物学的な親子関係がないという合意をしたとしても,それだけでACの親子関係が記載された戸籍を修正できるわけではありません。
A,BC間に争いがある場合はもちろん,争いがない場合も,Aは,親子関係が不存在であることの確認を求める家事調停を申し立てる必要があります。親子関係不存在,認知請求,離婚など人事に関する問題については,いきなり訴訟を提起することはできず,まずは,家事調停を申立てなければなりません(これを調停前置主義といいます。家事事件手続法257条)。
さらに,この調停で,3者が合意したとしても,それだけで直ちに,調停が成立するわけではありません。例えば,離婚調停の場合には,妻と夫が合意をすれば調停が成立となって,離婚ということになりますが,親子関係不存在の確認を求める調停の場合は異なるのです。
このような調停の場合には,いわゆる277条審判という手続をとる必要があります。
家事事件手続法277条
親子関係不存在確認の訴えについて・・・家庭裁判所は,必要な事項を調査した上,第1号の合意を正当と認めるときは,当該合意に相当する審判・・・をすることができる。
1 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立したとき
2 ・・・
要は,当事者間でA,Cに親子関係が存在しないことについて合意をしているような場合,家庭裁判所が,「必要な事項を調査」して,合意に誤りがないと認めることができれば,親子関係が存在しないという審判を下すということです。当事者が合意したからと言って,裁判所がその合意が誤りであると判断した場合には,277条の審判をすることはできません。身分関係は,できるだけ真実に合致している必要がある,当事者が自由勝手に決めてはいけない,という考え方が背景にあります。
「必要な事項を調査」する方法として分かりやすいのは,DNA鑑定です。ただし,277条審判をするために,必ずしも,DNA鑑定が必要なわけではありません。妊娠した時の状況や経緯等が明確になっていて,それを示す資料等がそろっていれば,DNA鑑定をせずに第1回の期日で事件を終了させることもあります。逆にいえば,当事者間に争いがない場合には,第1回の期日の前に準備を尽くしていれば,DNA鑑定等を行わず,調停をすぐに終了させることができるのです。第1回の期日に至るまでの準備が重要になります。
一方調停で合意が成立しない場合,あるいは,合意が正当と認められない場合には,調停は終了となります。このような場合には,Aは,親子関係不存在確認の訴えを家庭裁判所に提起することになります。親子関係の存否に争いがある場合には,調停や訴訟でDNA鑑定が行われるのが一般的です。DNA鑑定の費用は十万円くらいです。
[1] なお,Cはいわゆる「推定されない嫡出子」とします。「推定されない嫡出子」とは,婚姻成立後200日以内の出生子をいいます。「推定される嫡出子」だと手続が異なります
婚外子法定相続分の規定の違憲判決(最高裁平成25年9月4日大法廷決定)が与える影響
昨年9月4日,最高裁判所は,婚外子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号の規定を違憲だと判断しました。
多くの法律実務家は,近い将来違憲判決が出ることを予感していたように思います。むしろ,法律実務家の間の関心ごとは,「民法900条4号が違憲だと判断された場合,違憲とされた時点以後に行われた遺産分割協議,調停,審判等の効力はどうなるか」という点に移っていたと思います。すでに,平成23年9月の時点で,「もしも最高裁が民法900条4号ただし書の違憲判決を出したら」(東京大学法科大学院ローレビュー,2012年9月号)という論文が書かれており,私の弁護士仲間の間でも話題になっていました。
問題点をもう少し詳しく説明します。
本判決の事案では,被相続人が平成13年7月に死亡して相続が開始となっています。そこで,最高裁は,この相続が開始された平成13年7月時点で民法900条4号が違憲だったと判断しています。
平成13年7月以降平成24年9月4日まで,民法900条4号の規定が有効であることを前提として,たくさんの遺産分割協議,調停,審判等が行われてきました。そうすると,この期間成立した遺産分割協議,調停,審判等の効力はどうなるのでしょうか。また,現在,協議中の場合,あるいは調停を行っていたり,審判の手続を進めていたりする場合は,どのような処理がされるのでしょうか。
当然,最高裁判所もこの点について説明をしています。具体的には,「本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的になった法律関係に影響を及ぼすものではない」と判示しています。
つまり,
①遺産分割協議,調停,審判により法律関係が確定的になった場合は,その裁判や合意の効力は覆ることがない。
② 合意ができていなくて審判もでていないような場合には,民法900条4号が無効であることを前提として処理がされる。
ということです。
より具体的に言うと,
例えば,10年前に成立した遺産分割協議は,民法900条4号が違憲であることを知らずにしたものだから錯誤により無効であるという主張や,5年前に出された遺産分割審判は違憲である民法900条4号を適用して下されたものであるから再審事由があるというような主張はできないということです。
法的な理屈はともかく,結論としては分かりやすいと思います。ただし,「確定的となった法律関係」という判示の解釈は問題となる余地があります。
まず考えられるのが,明確に遺産分割協議は成立していないものの,各相続人がそれぞれ一定の財産を取得していて,そのまま時間が経過してしまっているような事案です。このような場合については,黙示的に「合意」がなされて,法律関係が確定的になったかどうかという問題に帰着すると思われます。
また,銀行預金債権等の債権債務の処理も問題となる余地があります。銀行預金のように,分割できる債権は相続開始により当然に相続人に法定相続分の割合で分割されるということになっています。そのため,相続人が,預金債権を引き出す際には,必ずしも,「合意」をする必要がありませんので(ただし,実際上は多くの場合合意があるとは思います。),どの時点で「法律関係が確定的」になったか不明確になるケースがあると思われます。
Newer Entries »